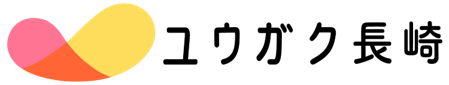鎌倉時代の「元寇」~鷹島沖で海底調査開始!元軍船の遺物は? 昭和のTVニュース
ユウガク | NBC 長崎放送映像のタイムマシーン
元寇(げんこう)といえば海底から引き揚げられた木製の大きな錨(いかり)を思い浮かべる方も多いかもしれません。この元寇(蒙古襲来)に関する水中考古学調査の歴史は始まってから40年あまりしか経っておらず、今も継続して調査が行なわれています。この調査が本格的に始まったのは昭和55年(1980年)で、この年の8月、NBCのカメラは東海大学の茂在教授率いる考古学グループの海上調査に同行しました。この日の調査では超短波を使って海底深く沈んでいる元寇船の遺物の正確な位置を確認しました。元寇は今から700年以上前の鎌倉時代、元軍が九州北部沿岸に2度に渡って襲来、鷹島沖で総勢14万人、4400隻の元軍船が暴雨風で壊滅したといわれています。この海域では古くから地元の漁師によって陶磁器や刀剣などが海底から引き揚げられていました。引き揚げられた壺の中から聞こえる音は元軍の兵士たちの怨霊の声ともいわれているそうです。